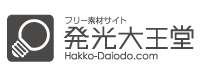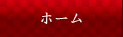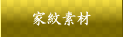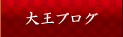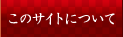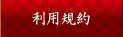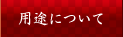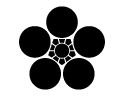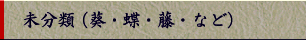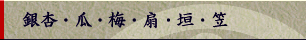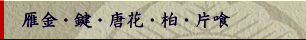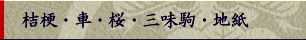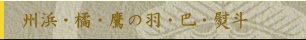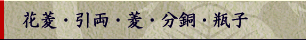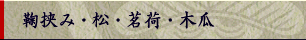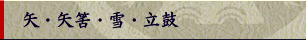右一つ巴
家紋・右一つ巴は、「オタマジャクシ」や「勾玉」に似た特徴的な形状を持つ図形を用いて構成される家紋の一群である『巴紋』の一種です。
この紋のルーツとなった原始の巴文様は、先史時代より世界各地で多発的に発生した普遍的な文様です。そのため「三つ巴紋」や「二つ巴紋」で知られる現代日本の巴紋についてもその起源や由来に明確な定説はなく、以下のような諸説が入り交じる状況となっています。
●『鞆=とも』と呼ばれる、弓を射るときに用いられた装身具を象ったとする説(「鞆の絵」から「巴」となったとも)
●雷の発する光(稲光)を表したとする説
●水の渦巻きを表したとする説
●ヘビがトグロを巻く姿を表したとする説
●「勾玉」を象ったとする説
●胎児を表したとする説
巴文様の広がりから家紋への流れ
以上のように、成立の経緯や由来については謎の多い巴の文様(紋章)ですが、その広がりはかなり早い時期から始まっており、すでに奈良時代ごろには使用が見られていたようです。
「高野山阿弥陀聖衆来迎図(国宝)」にあるように、雅楽の大太鼓の鼓面に描かれるものが象徴的な使用例に挙げられるほか、『春日権現験記絵』『前九年合戦絵巻』『年中行事絵巻』などといった絵巻物作品に登場することも確認されています。

11〜12世紀ごろには中央貴族の名門・西園寺家が、所有の牛車に巴紋を標したことで知られます。西園寺家の家紋が巴紋であるのは、このことが由来とされています。
巴紋は八幡宮のシンボルとしても有名
巴紋は、神社の神紋・社紋としても使用が広がっていますが、特に『八幡神』を祭神とする「八幡宮」系の神社で用いられることで知られます。全国44,000社を数えるとされる八幡宮の多くで巴紋が使用されているのは、主祭神である「八幡神」に関係したものでは?と見られているようです。

「八幡神」とは、15代天皇として記紀に記される『応神天皇』と同一視され、武運の神として清和源氏を始めとした数多の武家から尊崇を集めた神です。
「出生時に腕が鞆のように盛り上がっていた」と言い伝えられ、古事記には「大『鞆』和気命=おおともわけのみこと」の名で載るなど、弓矢の装身具である『鞆=とも』との関連が大変深い人物のようです。
また、「和風※諡号=しごう」(崩御後のおくり名)は「誉田(ほむた)天皇」(日本書紀)ですが、「ほむた」は「とも」の古語ですから、ここでも応神天皇と「鞆」の関連が指摘できます。
こうした「鞆」との関連により『鞆絵=巴』と応神帝が結びついたことが、巴紋が八幡神を象徴する紋章となった由来ともいいます。
武家による使用が目立つ巴紋
八幡神が武神として広く武家の信仰を集めた影響からか、そのシンボルであった巴紋は武家に使用の目立つ紋章のようです。
古くは、武家の黎明期である平安後期から近世期に至って存続した東国の名門武家である「宇都宮氏(右三つ巴)」「小山氏(左二つ巴)」「結城氏(右三つ巴)」「佐野氏((頭)左三つ巴)」らの使用が有名です。
室町幕政下の有力諸侯の一つであった播磨の「赤松氏(二つ引両に右三つ巴)」、長尾景虎を輩出した「長尾氏(九曜巴)」、小早川隆景を出した「小早川氏(左三つ巴)」なども巴紋を使用しました。
ほか、「九鬼氏(三頭右巴)」「板倉氏(九曜巴)」「有馬氏(有馬巴)」「伊那氏(左頭二つ巴)」「赤穂・大石氏(右二つ巴)」「香川氏(九曜巴)」「杉原氏(剣巴)」といった名だたる武家による使用も目につきます。
また、近世武家による巴紋の使用は、江戸幕府の直臣に限っても350余家の多数に上ったといいます。
以上が【右一つ巴】の解説でした。その他の巴紋については↓こちらから。
三つ巴紋について掘り下げて知りたい場合は↓こちらから。
二つ巴紋について掘り下げて知りたい場合は↓こちらから。
その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。
【右一つ巴】紋のフリー画像素材について
以下のリンクから家紋のベクターデータをダウンロードできます。無課金(フリー素材)です。規約はゆるゆるですが、念のため規約をご確認ください。「家紋のフリー画像を探しているけど、EPS・PDFの意味がよくわからない」という方は、ページトップの家紋画像(.png形式・背景透過・100万画素)をダウンロードしてご利用いただいても構いません。

※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。