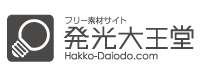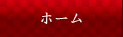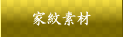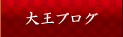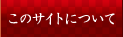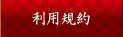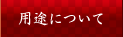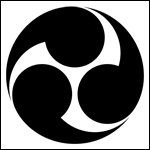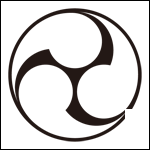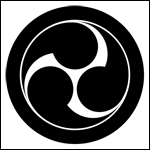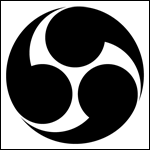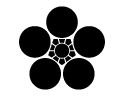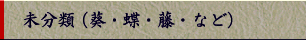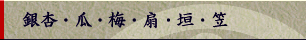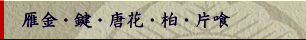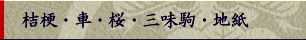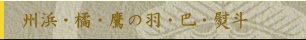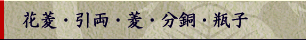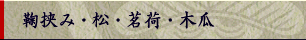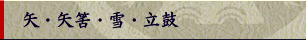三つ巴

【三つ巴】(みつどもえ)の語源となり、八幡宮の神紋・太鼓の文様・軒瓦の装飾などで広く知られる「三つ巴紋」の意味や由来を詳細に解説。武将や公家などによる著名な使用例や、種類一覧などもご紹介します。
『三つ巴』とは、主に「三つのものが互いに対立して入り乱れること」を指す言葉で、その語源は紋章・紋所の『三つ巴紋』に由来することは広く世間に知られているところです。
この紋章は、「オタマジャクシ」とも「勾玉」とも形容される図形3つを旋回状に配置したものですが、そのさまが「拮抗した3つの勢力が入り混じって争っているように見える」ことからこうした表現が定着したといいます。

それでは、こうした表現の由来となった「三つ巴紋」とはどのようなものでしょうか。ここからは、その知名度のわりに案外知られていない「三つ巴紋」についてのアレコレを詳しくご紹介したいと思います。
巴(三つ巴)紋の由来について
三つ巴紋は、『巴紋』の代表格ともいえる紋章です。ほかに「二つ巴紋」や「一つ巴紋」といった紋章もよく知られます。

現在、広い意味で『巴紋・巴文様』と呼ばれる図案は、古代のケルトや中国、そして日本など世界各地で多発的に発生したものであり、単一の起源を持つものではありません。
これらの巴文様は、単なる「うずまき」形であるものも多く、この原始の巴文様は現代の私たちが思い浮かべる勾玉のような形状をした巴紋と完全に同一視できるものではないと言えます。

ゆえに、「現代の巴」紋が「原始の巴」文様の直接的な発展系にあたるのかは不明であり、三つ巴紋の成り立ち・由来についてもこれといった定説は存在しないのが現状ですが、ここからはその諸説の中から有力なものをいくつかご紹介したいと思います。
「稲光をあらわす」説について
まず最初に「巴は雷の稲光を表している」とする説が挙げられます。この説によるとそもそも巴は、古代中国において稲光を表した「雷文」という渦巻き状の文様から徐々に変化したものとされます。

古代中国において描かれた「雷神(雷公)」は、周囲に連太鼓をそなえ、この太鼓を打つために槌や楔を手に携えているのが一般的ですが、これは「雷は雷公が太鼓を打って発生させるもの」という考えが背景にあるといいます。
「雷鼓」という言葉が、「雷神の持つ太鼓」または「雷鳴」そのものを意味することから、かつての太鼓は雷と密接に関連付けられていたことが分かります。
こうした「太鼓の音色を『雷の音(雷鳴)』とする」考えは、(音と対になる光の表現として)太鼓の鼓面に巴紋を描いてこれを『雷の光(稲光)』とする考えにつながっていったといいます。

「弓道の古い装身具である『鞆』を象った」説について
かつて弓を射るときに用いられていた装身具である「『鞆=とも』を象ったもの」とする説も有力です。「鞆」とは、矢を射た反動で弦が弓の持ち手に当たることを防止するために手首に巻き付けるもので、革製の丸く膨らんだ部分を内側にして革紐で結びつけて装着します。

巴の勾玉のような形状は、この装身具を象った図案(絵)である(または、巴の形状が鞆の絵のようだ)として『鞆絵=ともえ』の呼び名となり、のちに「うずまき」の意味を包有する「巴」の字が当てられたとしているようです。
「水の渦巻き」説などその他の説について
「ヘビがとぐろを巻く姿を表した」とする説は、漢字の『巴』が「ヘビが地面を這う」様子を象形したことに関連するようで、また「水の渦巻きを表した」とする説も、巴の字に「うずまき」の意味が含まれることから来ているのかもしれません。
ちなみに瓦の装飾に見られる巴は、(巴には水の渦巻きの意も含まれることから)「火除けのゲン担ぎ」の意味を持つといい、平安時代末期ごろの流行に端を発した習わしと伝わります。

先史・古代の装身具である「勾玉を象った」とする説については、巴の形状の類似に由来するものと考えられます。また「胎児を表した」とする説もこれと同様に形状に由来するものではないでしょうか。
以上、巴紋の由来として語られる主立った説を列挙してみましたが、残念ながら、現状はこのいずれの説も決定的なものとはいえないようです。
巴文様の広がりと三つ巴の紋章
成立の経緯や由来については謎の多い巴ですが、文様・紋章としての使用はかなり早い段階から始まっていたようで、すでに奈良時代には社会の至るところに広がりを見せていたようです。
特に『雅楽』の『大太鼓=だだいこ』の鼓面に描かれていた巴紋がその象徴的な使用例と言えるでしょう。
雅楽の大太鼓が巴(三つ巴)紋のルーツ?
「雅楽」とは、古代中国圏の宮廷儀式や儒教祭祀などで催された優雅で洗練された楽舞(音楽と舞)の一群にその端を発するものです。
日本には5世紀ごろより渡来が始まり、やがて朝廷に専門機関が設置されるほどの手厚い保護がなされ、古代・中世期には、宮中のみならず四天王寺・東大寺・興福寺といった巨大寺院においても盛んに催されたことから、当時は非常に大きな社会的影響力を持った芸能・芸術だったといえます。
「大太鼓」とは、その雅楽において用いられる巨大な膜鳴楽器(太鼓)をいいます。大陸文化を色濃く残す独特の外観を持つことで知られ、「火焔宝珠」を象った吊り枠台を含めれば、その全長は約7mにも及び、左右一対で設置されることが一般的です。

この左右の大太鼓のうち、向かって【左】方の鼓面には【三つ巴】が、【右】方の鼓面には【二つ巴】が描かれるのが古来よりの決まりごとのようですが、これは雅楽が古代の大陸から伝来した当時の様式を色濃く留めているものかもしれません。
巴のデザインが「日本発祥」か「大陸からの持ち込み」かについては判然としませんが、秦代の「陶胎漆鼎=とうたいしってい」なる漆陶器の蓋に三つ巴に酷似した模様が描かれていることから、少なくとも紀元前の中国には、すでに巴のような図案が存在していたことは確かだといえます。
広い認知を得ていた(三つ巴)の文様
宮中・貴族社会において、巴文様が服飾・調度・美術工芸品などの図柄に広く用いられ、伝統文様の一つとして重きをなすようになったのは、この雅楽の大太鼓が少なくない影響を与えたと見なされているようです。
史料に残る使用例を挙げれば、「高野山阿弥陀聖衆来迎図(国宝)」に描かれる大太鼓の装飾がやはり巴紋となっており、『春日権現験記絵』『前九年合戦絵巻』『年中行事絵巻』などといった絵巻物作品に頻繁に登場することが確認されています。

家紋「三つ巴」発生の端緒?西園寺家の家紋の由来
また、巴文様(三つ巴紋)は『牛車=ぎっしゃ』の文様としてもいち早く取り入れられました。
平安当時、貴族が日常の移動手段に用いた牛車には、その所有者を自他がひと目で判断できるよう、自家や個人にちなんだ文様を大きく標して「識別子」とする習わしが存在しました。
貴族社会における家紋の発祥は、この牛車に標された識別文様にあるとされています。近衛家の「牡丹」紋、徳大寺家の「木瓜」紋、花山院家の「杜若」紋、日野家の「鶴丸」紋あたりがよく知られる例です。
「三つ巴」の文様は、中央貴族でも屈指の名門である『西園寺家』が牛車に用いていましたが、西園寺家の家紋が「三つ巴」紋であるのは、やはりこのことに由来するようです。

その他、公家による三つ巴(系)の家紋の使用は、西園寺家庶流の橋本(尾長巴)・小倉(右三つ巴)・大宮(三つ巴)・山本(右三つ巴)の各家に、高倉流藤原氏・堀河家庶流の樋口家(釣巴)などが知られます。
八幡宮と三つ巴紋
三つ巴紋は、多くの神社・寺院の紋章としても使用が広がっていますが、その中でも特によく知られているのが、『八幡神』を祭神とする「八幡宮」系神社の神紋としての使用でしょう。

八幡神とは、応神天皇のご神霊であり、かつては伊勢神宮に次いで皇室の祖神に位置づけられた神です。「生まれながらの武神」と称された応神天皇と同一視されることもあって、『弓矢八幡』の別称でも知られます。
なぜ八幡神の別称は『弓矢』八幡なのか?
ところで、なぜ八幡神の別称は「弓矢八幡」だったのでしょうか?それは古代の武官や中世武士が重んじた「武家としての技能」の第一は(槍でも刀でもなく)『弓矢』であったという事実と関連があります。
つまり、かつての武家やそれを取り巻く社会にとって「弓矢とは武を象徴するもの」であるから、武神である「応神天皇=八幡神」の別称にも「弓矢」が用いられたというわけです。
八幡神のご神紋に三つ巴紋が用いられるのはなぜか?
また、応神天皇が「生まれながらの武神」とされたのは、「鞆を携えて生まれてきた」または「出生時に腕が鞆のように盛り上がっていた」ことに由来するといい、これもやはり「弓矢=武の象徴」という、武に対する日本古来の保守的価値観が土台になっていると言えるでしょうか。
応神天皇は、別名に「大鞆和気命=おおともわけのみこと」(古事記)を持ちますが、これはこの鞆にまつわるエピソードに由来したものといいます。
また、「※諡号=しごう」(崩御後のおくり名)は「誉田天皇=ほむたのすめらみこと」(日本書紀)で、実は「鞆=とも」には『ほむた』の読みもあり、「ほむた」は「とも」の古語ですから、応神天皇は諡号もまた「鞆」に由来するものということが言えます。
八幡神は、その信仰の広がりや知名度に反して謎の多い神ですが、神紋の三つ巴紋の由来に関しては、「鞆」との上記のような深い関係性に依るものとする説が有力視されているようです。
これまでを踏まえると、瓦に刻まれた三つ巴は「水の渦巻き」に由来するもの、太鼓に描かれた三つ巴は「稲光」に由来するもの、神社で見られる三つ巴は「八幡信仰」に由来するものとに大まかに分類ができるのかもしれません。
家紋「三つ巴」を使用の武家について
武神である八幡神は、やがて武家の棟梁・清和源氏の氏神に奉られると、のちに武家の守護神としても大いに信仰をあつめ、この八幡宮・神社の広がりとともに三つ巴紋もまた、全国的な普及を見せるに至ります。
武家による三つ巴紋の著名な使用例
古いところでは、古代末期ごろから栄えた上、戦国大名家としても知られた東国の名門武家である「宇都宮氏(右三つ巴)」「結城氏(右三つ巴)「佐野氏((頭)左三つ巴)」らの使用が有名です。
室町幕政下における屈指の名門である播磨の「赤松氏(二つ引両に右三つ巴)」、長尾景虎を輩出した「長尾氏(九曜巴)」、小早川隆景を出した「小早川氏(左三つ巴)」なども三つ巴系の家紋の使用でよく知られるところです。

また、琉球の王家である「尚氏」も「ひだりごむん」と称する「左三つ巴」を使用しました。他、武家による三つ巴系の家紋の使用例は、以下に挙げるとおりです。※それぞれに重複あり
【著名戦国武将】
●長尾景虎(九曜巴)
●小早川隆景(左三つ巴)
●結城秀康(右三つ巴)
●九鬼嘉隆(三頭右巴)
●山本勘助(左三つ巴)
●清水宗治(三頭右巴)
●板倉勝重(九曜巴)
●佐野昌綱(左三つ巴)
●宇都宮国綱(右三つ巴)
●有馬豊氏(有馬巴)
●岡部元信(左三つ巴)
●赤松義祐(二つ引両に右三つ巴)
●香川之景(九曜巴)
【中世武家】
●宇都宮氏(右三つ巴)
●伊予・宇都宮氏(三つ巴)
●筑後・宇都宮氏(三つ巴)
●城井氏(三つ巴)
●多功氏(三つ巴)
●芳賀氏(三つ巴)
●武茂氏(三つ巴)
●塩谷氏(三つ巴)
●結城氏(右三つ巴)
●(藤姓)足利氏(三つ巴?)
●佐野氏((頭)左三つ巴)
●阿曽沼氏(三つ巴)
●曾我氏(浪に左三つ巴?三つ巴に雲?)
●赤松氏(二つ引両に右三つ巴)
●杉原氏(剣巴)
●香川氏(九曜巴)
●長尾氏(九曜巴)
●山田氏(鱗右三つ巴)
●丸氏(三つ盛り右巴)
●芝山氏(三つ積み右三つ巴)
●山下氏(枡形に左三つ巴)
●金山氏(一つ引きに二つ右三つ巴)
●太平氏(五瓜に左三つ巴)
●土肥氏(左三つ巴)
●沼田氏(左三つ巴)
●小早川氏(左三つ巴)
●新開氏(左三つ巴)
●備中清水氏(左三つ巴(三頭右巴))
●三河山本氏(左三つ巴)
●摂津有馬氏(有馬巴)
●板倉氏(九曜巴)
●九鬼氏(左三つ巴(三頭右巴))
●岡部氏(左三つ巴)
●三河林氏(左三つ巴下に一文字)
●琉球国王・尚氏(左三つ巴=ヒジャイグムン)
【江戸幕府旗本】(定紋のみ選抜・大名家の分家含む)
●朝岡氏(左三つ巴)
●朝比奈氏(左三つ巴)
●芦野氏(一の字に左三つ巴)
●有馬氏(有馬巴)
●赤松流・石野氏(左三つ巴)
●板倉氏(左三つ巴)
●宇都野氏(左三つ巴)
●岡部氏(左三つ巴)
●小浜氏(左三つ巴)
●筧氏(左三つ巴)
●久貝氏(左三つ巴)
●藤原北家流・佐久間氏(左三つ巴)
●佐山氏(左三つ巴)
●杉山氏(庵に左三つ巴)
●曾根氏(丸に左三つ巴)
●高井氏(左三つ巴)
●中条氏(釣巴)
●柘植氏(三頭右巴)
●長尾氏(左三つ巴)
●小笠原流・中島氏(九曜巴)
●長島氏(一文字に左三つ巴)
●贄氏(敷瓦に左三つ巴)
●土方氏(左三つ巴)
●船越氏(左三つ巴)
●別所氏(左三つ巴)
●松崎氏(左三つ巴)
●松野氏(左三つ巴)
●皆川氏(左二つ巴)
●村瀬氏(九曜巴)
●柳世氏(左三つ巴)
●石亀流・山川氏(左三つ巴)
替紋に三つ巴を用いる【江戸幕府旗本】(大名家の分家含む)
●雨宮氏(左三つ巴)
●佐野流・飯塚氏(左三つ巴)
●石丸氏(三つ巴)
●宇津氏(三つ巴)
●武田流・大井氏(左三つ巴)
●片岡氏(左巴)
●鎌田氏(左三つ巴)
●桑原氏(左巴)
●境野氏(左三つ巴)
●篠山氏(三つ巴)
●菅原流・佐野氏(左三つ巴)
●佐橋氏(左三つ巴)
●進氏(左三つ巴)
●杉原氏(剣巴)
●高山氏(三つ巴)
●田中氏(左三つ巴)
●田村氏(左巴)
●織田流・柘植氏(左三つ巴)
●三枝流・辻氏(三つ巴)
●波多野流・中島氏(九曜巴)
●永島氏(左三つ巴)
●真周系・彦坂氏(三つ巴)
●清和源氏流・平野氏(左三つ巴)
●細田氏(左三つ巴)
●本間氏(三つ巴)
●波多野流・松田氏(左三つ巴)
●松波氏(左巴)
●三田氏(左三つ巴)
●宮崎氏(左三つ巴)
●村田氏(三つ巴)
●八木氏(右三つ巴)
●江守流・山川氏(右三つ巴)
以上、全てはとても挙げきれませんが、巴紋の使用は江戸幕府の直臣に限っても350余家の多数に上ったといいます。
三つ巴系の紋章が、神社の神紋・武家の家紋としてこのように多数に及ぶのは、やはり八幡信仰による影響が大きいと言え、現代における三つ巴紋の使用や知名度の広がりはこうした要因が大きいと考えてよさそうです。
三つ巴紋の左右の呼称問題について
渦巻き型の紋章である三つ巴紋には、その渦巻きの回転方向が「左巻き」のものと「右巻き」のものがそれぞれ存在し、その呼称も「左三つ巴」と「右三つ巴」に分かれます。

長くなるのでここでは「問題」の生じた経緯等については省きますが、要するに「何をもって左右とするか」の基準が統一されていないことにより、名称や分類の混乱が生じているということです。
『左右の基準』とは、回転方向の先頭を巴の勾玉状の形状の『頭(丸い部分)側』とするか『尾(細く尖っている部分)側』とするかであり、たとえ同一の三つ巴紋であっても、どちらを回転の先頭にするかによって「左三つ巴」とも「右三つ巴」とも言えてしまうというわけです。

この問題に対する当サイトの方針といたしましては、「尾側先頭」を基準とした左右の命名規則に統一しておりますのでご了承ください。
三つ巴紋のいろいろ
二つ巴紋について掘り下げて知りたい場合は↓こちらから。
巴紋全般については↓こちらから。
その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。