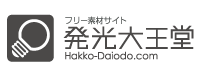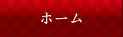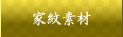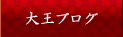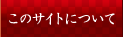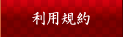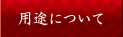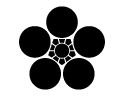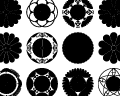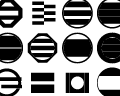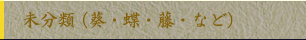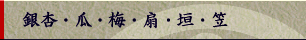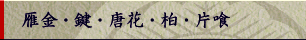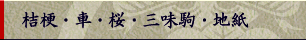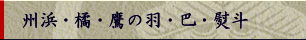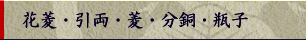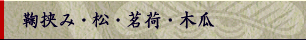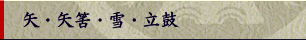隅立て角に隅立て一つ目
家紋・隅立て角に隅立て一つ目は、鹿の子絞り(絞り染め技法の一つ)の模様を象った紋章である「目結=めゆい」紋の一種です。

目結紋について
鹿の子絞りは古くは「纐纈=こうけち」といい、またこの技法は、布地を糸で "結" って(穴の空いた方形の模様である)"目" を作り出すことから「目結(目交)」ともいいました。
目結紋種の分類
目結紋は、鹿の子絞りによって作り出される模様である「目」を基本とし、この「目」の数と角度の違いによって種類が分かれます。
目が1個であれば「一つ目(結)」、3個で「三つ目(結)」、12個で「十二目(結)」となり、角度でいえば、目を水平に置いたものは「平=ひら」、斜め45度に角を立てたものは「隅(角)立て=すみたて」となるのが目結紋の分類の基本です。
あとは他の紋種と同様、円形や方形などの図形で紋章を囲ったり、黒地の図形を地色で抜いたり、図形を(面ではなく)線で表現したり、折る・捻る・結ぶなどの変形のバリエーションを持ちます。
目結紋(文様)の広がり
ほかの多くの家紋と同様、目結紋も目結の文様から派生したものですが、目結文様は『源平盛衰記』『春日権現験記絵』『保元物語』などに衣服や幡などの文様として描写があることから、平安時代にはすでに文様として一般化していたようです。
また、上級貴族である九条家が冠に用いる文様としても知られた存在でした。
目結紋の使用について
目結紋は武家を中心に普及した紋章で、長らく近江国を拠点に繁栄した「宇多源氏・佐々木氏」の一族による使用が特に知られ、「武藤氏」の一流とその後裔である「少弐氏」も一族での使用が見られます。
佐々木氏と目結紋
佐々木氏は、第59代・宇多天皇の後裔氏族で、平安時代後期ごろに荘官として管理・運営した近江国・佐々木荘を根拠地としたことで発足した氏族です。
佐々木氏は、鎌倉幕府成立の功臣として名高い「佐々木四兄弟」や、発足直後の室町幕府で重きをなした「佐々木(京極)道誉」ほか、後裔に「六角氏」「京極氏」「尼子氏」「佐々氏」などの戦国大名家を抱えることでも著名な氏族です。

当初、佐々木一族において目結紋を使用したのは、佐々木氏の嫡流系統である「定綱流」であり、その祖である佐々木四兄弟の長男「佐々木定綱」と子の信綱は、「摂関・九条家」に家礼として仕えていました。
当時、目結は中央貴族でも屈指の名門である九条家の冠の文様として名高いものであったことから、定綱流が家紋に目結を使用したのは、この九条家との関係性に由来するものではないかという説が有力です。

定綱流の目結紋は、後継氏族の嫡流である「六角氏」や庶流の「京極氏」「大原氏」「高島氏」などに引き継がれたほか、別系統である「朽木氏」「平井氏」「竹腰氏」「青地氏」「伊庭氏」「亀井氏」「間宮氏」などにも広がり、「目結紋は佐々木氏の定紋」とも言うべき状況を形作るに至りました。
近世以降の武家では、幕府直臣に限っても目結紋の使用110数家に対して、77もの家が佐々木氏族となっています。
少弐氏と目結紋
藤原秀郷流「武藤氏」族の武藤頼平の後裔にあたる「少弐氏」や「大宝寺氏」も目結紋の使用で著名な存在です。この武藤氏の系統が目結紋を使用するのは、源(八幡太郎)義家に賜った「寄せ懸け目結の旗」に由来するといいます。
少弐氏とは、頼平の子(猶子)である武藤資頼が、九州・太宰府の次官級である「太宰少弐」に任じられたことに由来する一族です。長らく九州北部で重きをなした九州地方屈指の名門武家で、庶流の「筑紫氏」「肥前平井氏」「肥前馬場氏」なども目結紋を用いる氏族だったようです。
また武藤氏族ではないものの、少弐氏の被官であり、長らく対馬を支配した豪族として知られる「宗氏」も目結紋を使用する一族です。
その他の目結紋の使用
元寇を題材とした絵巻物である「蒙古襲来絵詞」には、竹崎季長が「三つ目結に吉の字」で、また室町時代の家紋集録書である「見聞諸家紋」には、椎谷氏が「四つ目」、二松氏・飯田氏が「三つ目」、斎藤氏・本庄氏が「九つ目」、能勢氏が「十二目結」、本間氏が「十六目結」で掲載されています。
以上が【隅立て角に隅立て一つ目】の解説でした。その他の目結紋については↓こちらから。
その他の家紋の一覧ページは↓こちらから。
【隅立て角に隅立て一つ目】紋のフリー画像素材について
以下のリンクから家紋のベクターデータをダウンロードできます。無課金(フリー素材)です。規約はゆるゆるですが、念のため規約をご確認ください。「家紋のフリー画像を探しているけど、EPS・PDFの意味がよくわからない」という方は、ページトップの家紋画像(.png形式・背景透過・100万画素)をダウンロードしてご利用いただいても構いません。

※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。