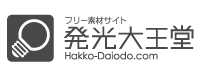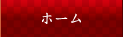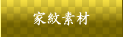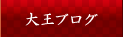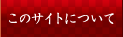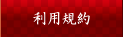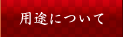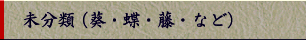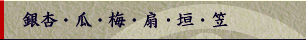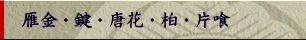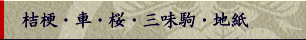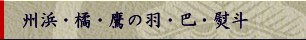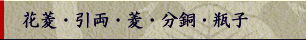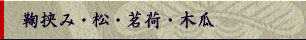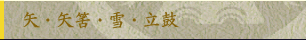外雪輪に抱き茗荷

外雪輪に抱き茗荷紋は雪紋の一種で、六角形の雪の結晶をモチーフとして、輪郭を曲線で繋いで図案化したものです。
雪は、古来より豊作の瑞兆とされ、平安時代の朝廷では、初雪が降ったその日に臣籍皆参内し(初雪の見参という儀式)、特別に褒美を賜る事もあったようです。
やはり、文様として使用されたからには、それなりの謂れのようなものは有ったのでしょうが、豊作の瑞祥として捉えられていたというのは、初耳でした。
雪の結晶というのは六角形ですが、顕微鏡のない時代に、雪紋もきっちり六角の形で図案化されているのは、ちょっとしたミステリーを感じてしまいます。当時の人は、雪の結晶の事を「六花」と呼び、ちゃんと認識していたようです。
雪紋も少なくない種類が作られていますが、単体として家紋に用いられる事例は、かなり少なかったようで、専ら、雪輪や外雪輪という、任意の文様を囲う枠のような利用が多かったようで、その傾向は現代にも通じているようです。
文様としての雪輪は、冬の情景を表すときや、涼しさを演出されるために夏の着物に使われるなどの由来があるのですが、任意の紋を雪輪で囲って、雪の家紋として用いられた謂れとは何だったのか、それは定かではありません。
何故、外雪輪で抱き茗荷紋を囲うのでしょうか。熨斗輪や五瓜と同じく、すでに成立している家紋を囲って、別の家紋にする類のものは、その由来に定説は存在しないのかもしれませんね。
スポンサードリンク
※「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選んで下さい。